
企業が外国人材を受け入れる上で、「日本と海外の職場文化の違い」を意識することが非常に重要なテーマとなっています。実際に、初めて欧米からのインターンを受け入れる企業様から「実際に接してみると、新しい視点や価値観の違いを感じる」という声をいただくことが少なくありません。
出入国在留管理庁の「令和6年度在留外国人に対する基礎調査」では、日本で20年以上働く外国人からも、「実績を出しても昇進や研修の面で不利を感じる」「制度はあっても情報が届かず、自分で調べるしかない」といった声が挙がっています。また、「職場では評価され尊敬されていても、長期的なキャリア人材として会社に見られているかというと、まだ課題を感じる」という指摘もありました。こうした声からは、日本企業に根付く“空気を読む文化”や“曖昧な評価基準”が、外国人材の成長や定着を難しくしている現実が見えてきます。
文化の違いは、ときに戸惑いやすれ違いの原因になります。でもそれは決してネガティブなものではなく、むしろ新しい価値を生むチャンスでもあるのです。日本では「当たり前」とされている習慣も、外国人から見ると「どうしてそうなるの?」と疑問に感じることがあります。文化に優劣はなく、どの価値観もその国の背景や歴史に根ざしています。そうした違いを理解しようとする姿勢が、信頼あるチームづくりにつながります。
これからの企業には、多様な価値観を尊重できる柔軟性が求められます。その第一歩が「違いを知ること」。この記事では、欧米のインターンが実際に戸惑った日本の職場文化について、事例を交えながらご紹介していきます。
外国人インターンを迎える際に、まず知っておきたいのが「職場文化の違い」です。欧米では、日本に比べてインターンシップの活用が盛んであり、大学の単位に含まれていることも多いです。そのため、彼らは学生のうちから社会経験を積み上げていくのが一般的になっています。また、キャリアアップを目的とした転職も当たり前であり、人材の流動性が日本よりも高いです。そのため、日本で一般的であった終身雇用という制度はアメリカでは存在しません。
欧米と日本では、働き方やコミュニケーションのスタイルに違いがあり、それが時に誤解や戸惑いを生んでしまうことがあります。
たとえば、日本では「報連相(ほうれんそう)」が重視されますが、欧米では、「任された仕事は自分の裁量で進める」のが一般的です。逆に細かく報告することが「信頼されていない」と感じられてしまうこともあります。欧米では、基本的に個人主義の考えが強いため、何か不満があっても、はっきり自己主張をしない限り「不満はない」と見なされてしまう傾向があります。日本ではあいまいな表現や遠回しな言い方が多いのに対し、欧米ではストレートに意見を伝えるのが普通。そのため、外国人インターンが率直な意見を言っただけなのに「空気が読めない」「生意気」と誤解されてしまうこともあります。
また、上下関係のとらえ方も異なります。日本では年功序列や敬語の文化が強く残っていますが、欧米では上司にもファーストネームで話しかけることが一般的な国も多く、最初は驚かれるかもしれません。
こうした違いを知っておくことで、企業文化や組織風土の違いを前もって伝えることができ、インターンもより安心して力を発揮できる環境づくりに繋がります。
ここでは、実際に弊社がサポートした企業様の外国人インターン戸惑いエピソードをいくつかご紹介します。文化の違いは、現場でこそリアルに感じるものです。
①ハッキリ言ったら注意された
オランダ出身のインターンは、会議で上司から「どう思う?」と聞かれたので、自分の意見を正直に話しました。ところがその後、他の社員から「あの場ではあまりハッキリ言わない方がいい」と指摘され、戸惑ったといいます。そのインターンにとっては、率直に伝えることが「効率的で誠実なコミュニケーション」だと考えていたため、自分の意見を素直に伝えたつもりでした。ところがその時は、状況や周囲の空気を読むことが優先される場面だったようで、思わぬ戸惑いを感じたようです。
②残業=マナー?の壁に戸惑い
アメリカから来たインターンは、定時で仕事を終えようとすると、周囲がまだ残っていることに気づき「帰っていいのかな…」と不安に。結局その日は少し残り、他のスタッフが帰る時に一緒に退社したそうです。後日「自分だけ先に帰るのはダメなのか」と上司に相談した際、日本にはチームとしての協力や空気を読む文化があることに気がついたそうです。
こうした小さな戸惑いの積み重ねは、モチベーションや信頼関係に影響することもあります。逆に言えば、企業側が文化の違いを事前に理解し、それをインターン側と共有する時間をきちんと設けるだけでも、インターンにとっては安心感につながり、自分らしく働きやすくなります。
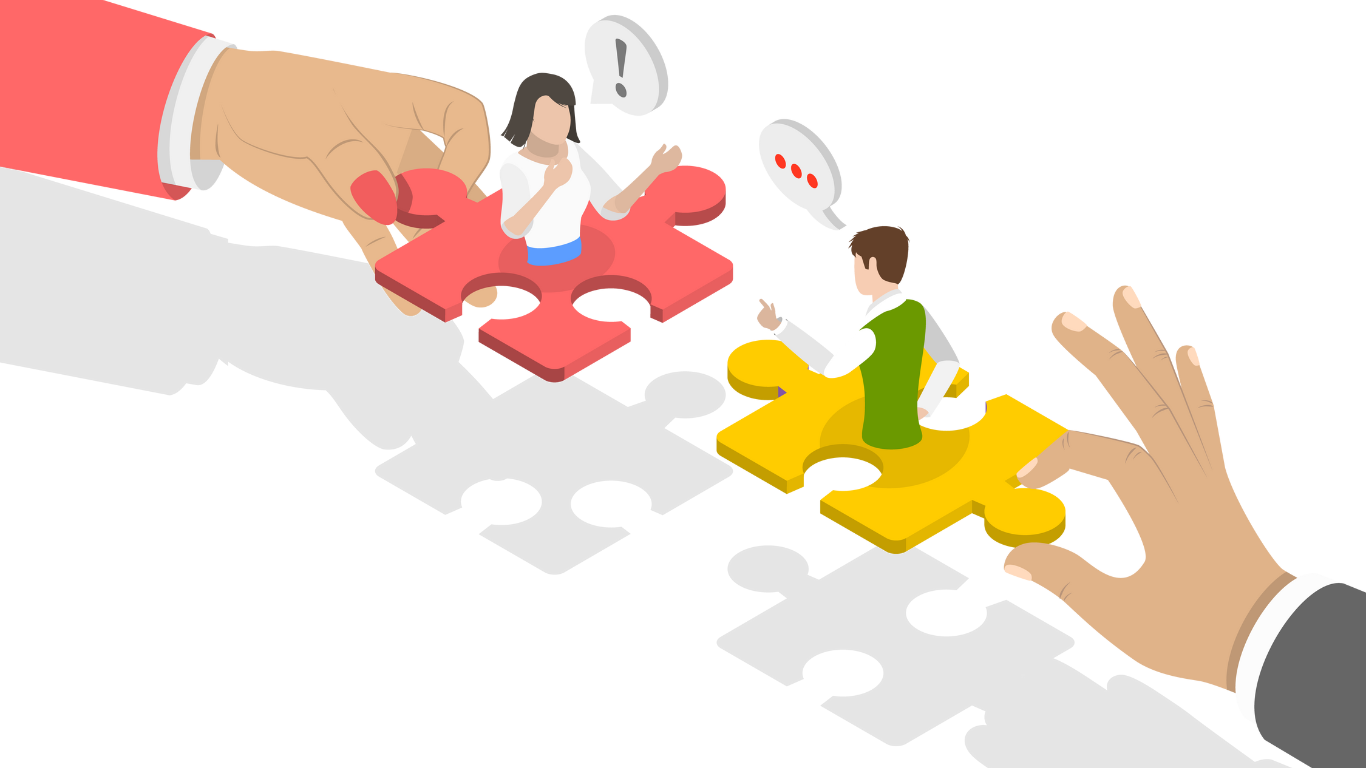
企業が外国人インターンを受け入れるうえで、文化の違いを理解することは配慮だけでなく、企業全体の成長や変化を促す大切なステップにも繋がります。Story Agencyとして多くの企業を支援してきた経験から言えるのは、文化の違いを前向きに受け入れている企業ほど、社内の雰囲気が自然とオープンになっていく傾向にあること。雰囲気がオープンであることは社員同士の対話が活性化し、チームの柔軟性も高まりやすいです。また、異なる視点を持つ人材が加わることで、新しい発想や改善のアイデアが生まれやすくなります。「この仕事のやり方って、こう変えた方がもっとスムーズでは?」という外国人インターンからの一言が、大きな業務改善につながった例もありました。文化の違いを乗り越えるプロセスは、組織に新しい視点や気づきをもたらします。そしてそれは、「どんな人にとっても働きやすい職場づくり」への第一歩にもなります。
では、実際に企業側が文化の違いにどう対応すればよいのでしょうか。ここでは、Story Agencyが支援してきた企業の実例をもとに、効果的だった3つの取り組みをご紹介します。
①オリエンテーションで不安を解消
インターン受け入れ前のオリエンテーションや事前説明が鍵になります。日本特有の「報連相」や暗黙のルール、職場でのマナーなどを丁寧に伝えることで、インターンの不安が大きく減ります。特に英語対応の社内マニュアルがあると、安心感がぐっと高まります。
②「社内の相談役」づくり
社内メンター制度の導入も効果的です。特定の社員がインターンの相談役となることで、業務上の疑問だけでなく、文化や人間関係に関する悩みも気軽に共有できる環境が整います。
③フィードバックが信頼を育てる
定期的な1on1面談やフィードバックの場を設けることも大切です。欧米出身のインターンは特に「フィードバック」や「成果に対する評価」を重視する傾向があるため、小さなことでも言語化して伝えることが信頼につながります。
これらの取り組みを通じて、「違って当たり前」の感覚が社内に浸透し始めると、インターンだけでなく社員にとっても働きやすい職場づくりにつながっていきます。Story Agencyでは、来日後すぐにインターン向けの共通オリエンテーションを実施しており、日本の働き方や職場マナーをあらかじめ伝えています。また、企業とインターンの間に立って、インターンシップ期間中も双方の相談役としてサポートしています。必要に応じてインターン本人にもフィードバックを行い、安心して働ける環境づくりをお手伝いしています。

外国人インターンを受け入れるうえで、「文化の違い」は避けて通れないテーマです。けれど、それは決して障壁ではなく、新しい価値を生むきっかけにもなります。たとえば、当たり前だと思っていた職場の常識や働き方を見直すチャンスになりますし、「なぜこうしているのか?」と自分たちのやり方を問い直すことで、固定観念から抜け出すヒントが見つかるかもしれません。そうした気づきが、組織の成長を後押しする大きな力になります。これからの企業には、多様性への理解や共有、実践が求められます。「外国人だから仕方ない」ではなく、「違うって面白い」「その考え方、新鮮だね」と言えるチームづくりが、未来につながるはずです。
外国人材の受け入れに興味がある企業の方は、まずはインターンシップという形で一歩踏み出してみるのも一つの方法です。小さなきっかけが、職場に新しい視点や気づきをもたらしてくれるかもしれません。